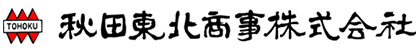社長だより vol.19
【文房四宝 その2】
『「こんなことになるんだったら・・・」信助がうつむいて、低い声で言った。「いや、こうなるとわかってたら、あのとき…」「だめよ」おつえは鋭い声でさえぎった。「それを言っちゃだめ、信助さん」町にたそがれ色がたちこめるころ、おつえは妹の家を出た。~ 信助が言いかけた言葉を思いだしたとき、おつえは不意に目に涙があふれ、頬を伝うのを感じた。信助が何を言おうとしたかはわかっている。だが、過ぎた歳月は、もう取り返すことができないのだとおつえは思っていた。』
(昭和54年5月号太陽”特集小説 藤沢周平 歳月より、挿絵:中一弥“)
引用の部分は、おつえが妹のさちと信助が暮らす裏店に初めて出向いた日のこと。さちが二人の関係を知ってか知らずかお茶菓子を買いに出て二人だけになった時の場面だ。おつえが嫁いだ材木商上総屋が間もなく人手に渡ろうとしている間際だった。挿絵は信助。
墨 墨というと先ごろ亡くなられた富田勲さんの、NHK新日本紀行のテーマソングと共に紀州で裸一貫、真っ黒になり墨を練るあの光景を思い起こす。墨は松煙墨に限ると聞くが、あまりの重労働で昭和の三十年代でほぼ松を燃やす煙は消えたそうだ。手元にある墨は油煙墨だろう。ナタネ油を燃やして煤をとったものだ。しかし、まだ摩っていないこの墨(写真上段の左端)は価格から見て松煙墨かもしれない。購入した時、産地を聞いておけばよかった。
墨は乾いてから、働き時が30~40年後に最もいい色が出ると言われる。さすれば今がちょうど摩り時だ。しかし文箱から漂う墨の香は何とも落ち着くのである。あと何年生きられるかわからないが心を摩ることに徹したほうがいいのかもしれない。気に入った相性のいい硯でゆったりと紙に向ってこの墨を摩っている自分を思うと楽しくなってくる。墨は摩ればなくなるが墨色として残る。黒色ではあるが様々な墨色に思いを馳せるとますます楽しみになってくる。現代の名工、墨匠 港 竹仙の手になる墨跡を見たいものだ。きっと私はこれからも目肥えを楽しんでゆくのだろう。
紙 友人からお膳を譲り受けた。お膳を包んでいた袋紙、厚手ながらごわごわ音もせずしなやかで感触は布だ。輪島と「印」があるので地域は離れているものの、越前和紙か若狭和紙と勝手に思っている。一方、この存在感のある「印(6×9センチのほぼ黄金比)」が読めない。気になる。読める人はきっと川連(かわつら)だ。「川面漆器伝統工芸館」に出かけた。訪館は初めてだ。おさえがちの外観とは違い一歩はいると穏やかな華やかさに気分が高揚する。玄関ホールに水滴の入った硯箱が展示してあった。蒔絵もいいがデザインが繊細で透明感がありことのほか上品だ。簡単にお断りされるかなと思いながら「印」を読んでもらった。“詳しいことはわからないので理事長に聞きます”とのこと。日曜にもかかわらず、ものの数分である理事の方に駆けつけていただいた。お膳を一目で“『本物の伝統輪島塗です。時代は大正あたり、読み方は「朱(しゅ)の方が、ろいろ とぎだし、とくさん ぬのきせ ほんかたぢ」』”、併せて製法も丁寧にお話しされた。数週間のもやもやが氷解した。館員の方々にも随分とお世話になった。もう一度ゆっくり訪ねてみよう。
左の紙束は茶箱に残された半紙。半切も相当数ある。シミがはいらないようたまに取り出しては眺めている。半紙の中には、画宣紙(がせんし)の他、○○さんからのプレゼントと書いたものがある。懐かしい方の名だ。「手すき、雁皮(がんび)、シミなし」などと書かれたものもある。きっと大事にしまっていたものだろう。『奉書紙』や『鳥の子紙』と思われる紙もある。このまま残してももったいない。寝室の障子に張ったらさぞかし贅沢だろうなあ。
平成28年7月