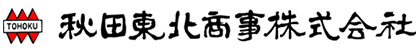カテゴリー : 社長だより
社長だより vol.112
令和6年も半分の6ヶ月が過ぎ、7月がスタートしました。6月23日に梅雨入りした秋田県、雨が降る日も多く毎日ジメジメしています。先月も取り上げましたが、ウェザーニュースでは「今年は全国的に梅雨入りの時期は“平年より遅く”、梅雨明けの時期が“平年並み”の予想です。梅雨期間の雨量は全国的に“平年並みか多く”なる見込みですが、特に6月下旬から7月上旬にかけて大雨に注意が必要です。」と発表しています。今のところは発表通りですから、これからは大雨に注意して日々の生活を送りましょう。そして待ち遠しい秋田県を含む東北北部の平年の梅雨明けは「7月28日頃」です。
意外と梅雨、、、長いですね!
突然ですが、皆さんは“ペップトーク”という言葉、内容をご存じですか?私も、ある会で知り合った仲間から教わりました。“ペップトーク”とは、もともとアメリカでスポーツの試合前に監督やコーチが選手を励ますために行なっている短い激励のスピーチです。「ペップ(PEP)」は英語で、元気・活気・活力という意味があり、日本を代表するアスレチックトレーナー岩﨑由純氏がアメリカのスポーツ現場で学んだ「勇気を与える感動のスピーチ」を、自分、家族、仲間に伝える為に確立したコミュニケーションスキルの事になります。
実は先日、その仲間が日本ペップトーク普及協会の講師であるという事で“ペップトーク”について講演をしてくれました。非常に興味深く、参考になりましたので以下に基本をご紹介させて頂きます。
選手がスポーツの技や力を磨くようにリーダーは言葉の力を磨く事『脳科学×心理学』で“ペップトーク”を活用する事が出来ます。特徴は「短く」「分かりやすく」「肯定的な」「魂を揺さぶる」トークで、前向きな背中の一押しをする声掛けです。ポジティブな言葉を使う事を心掛けて、相手の状況を受け止めて、ゴールに向かった短くて分かりやすい、人をその気にさせる言葉がけで相手を勇気づけるトークです。
“ペップトーク”は4ステップあり、仕事などで上司が部下に活用すると次のようになります。
①受容(事実の受け入れ)・・・『どうした?』
②承認(とらえかた変換)・・・『それは〇〇って事だよね』『これまで◇◇はやってきたね』
③行動(してほしい変換)・・・『どうしたい?』『後、僕は何が出来る?(手伝える?)』
④激励(背中の一押し)・・・『じゃあ、やってみよう!』
特に気を付ける事は2つあります。
『②承認(とらえかた変換)』ではポジティブが必須で“過去ではなく未来”“短所ではなく長所”を意識した言葉、「問題が発生した」ではなく「成長のチャンス」、「時間にルーズ」ではなく「おおらかで優しい」などといった考え方が重要です。事実はひとつですが解釈は無数にあるのです。
『③行動(してほしい変換)』でもポジティブが必須となり“してほしくない(否定)”ではなく“してほしい(肯定)”言葉、「嘘をつくな」ではなく「正直に話そう」、「事故するな」ではなく「安全運転で」などといった言葉のチョイスが重要です。脳は“肯定”と“否定”を区別できないと言われています。
言葉が変わると気分が変わり、気分が変わると思い込みが変わります。勿論、結果も変わります。
最後に超有名な“ペップトーク”を以下に記します。
「僕から1個だけ。憧れるのを、やめましょう。ファーストにゴールドシュミットが居たりとか、センターを見たらマイク・トラウトが居るし、外野にムーキー・ベッツが居たりとか。野球をやっていれば、誰しもが聞いた事のあるような選手達がいると思うんですけど、今日1日だけは憧れてしまったら越えられないので。今日僕たちは超える為に、トップになる為に来たので。今日1日だけは彼らへの憧れを捨てて、勝つことだけ考えていきましょう。さあいこう!」
(皆さんも記憶に残っていると思いますが、2023年WBC決勝戦前に大谷翔平選手が円陣で語った言葉です。社長だよりVol.97でも取り上げていましたが、大谷選手が“ペップトーク”を認識しているか否かは定かではありません。)
今回ご紹介した“ペップトーク”について、皆さんはどう思いましたか。私は基本的にはポジティブシンキングを心掛けています。しかし普段の自分の思考をよく思い出すと、事実を受け入れて(①受容)、②承認(とらえかた変換)と③行動(してほしい変換)が無く、すぐにポジティブシンキングでやっている(④激励)ような気がします。今回の講演で理解を深めた“ペップトーク”で特に気を付けなくてはいけない部分「承認」「行動」を今後は意識して、自分、家族、仲間に“背中の一押し”となる声掛けをしていこうと思いました。
余談になりますが、講演会終了後に「自分は息子の試合前に“絶対に負けるな!”“三振だけはするな!”とか言ってる。それが駄目なんだな。」と別の仲間が話をしていました。
過去に自分が子供達に話をしていた言葉を思い出してみると常に「楽しめ!」と言っていたと思います。我が家の子供達にとって“背中の一押し”なっていたのか、、、分かりません。
(私の理解力では色々と間違っているかもしれません。仲間の『Hさん』、勘違いや間違い等がある場合はお許しを頂ければ幸いです。)
長いようで短い1ヵ月。又1ヵ月後に更新致しますので、お付き合いを宜しくお願い致します。
社長だより vol.111
6月がスタートしました。6月と言えば、やはり“梅雨”です。沖縄地方や奄美地方では既に梅雨入りしていますが、全国的にはこれからになります。ウェザーニュースでは5月15日に「今年は全国的に梅雨入りの時期は“平年より遅く”、梅雨明けの時期が“平年並み”の予想です。梅雨期間の雨量は全国的に“平年並みか多く”なる見込みですが、特に6月下旬から7月上旬にかけて大雨に注意が必要です。」と発表しています。秋田県を含む東北北部の平年の梅雨入りは「6月15日頃」です。湿気や雨は決して心地が良い訳ではありませんが、必要としている方や環境があるのも事実です。我慢?ではありませんが、どんな環境でもしっかり受け入れて日々の業務や生活を送っていきましょう。
先日ある講演会に参加させて頂きました。ファシリテーター?と小説家先生による対談形式の講演会は時間が過ぎる事も忘れるくらい掛け合いや話の内容が面白く、色々と考えさせられる時間でした。今回はその講演会の中で小説家先生が話をされた言葉をご紹介したいと思います。
『副詞や形容詞を省けば良い文章になる』
学生時代には勉学ではなく、部活や上下関係について一生懸命に学び、頑張ってきた自分なので「“副詞?”“形容詞??”聞いた事はあるけど、、、」などと考えてしまいました。
勿論、理解している方も多々いらっしゃると思いますが、確認の意味や答え合わせのつもりでお付き合い頂ければ幸いです。(お恥ずかしいですが、私はしっかり学び直します!)
“副詞”と“形容詞”の意味は以下の通りです。(辞書の引用になります。)
【副詞】
自立語で活用がなく、主語にならない語のうちで、主として、それだけで下に来る用言を修飾するもの。事物の状態を表す状態副詞(「はるばる」「しばらく」「ゆっくり」など)、性質・状態の程度を表す程度副詞(「いささか」「いと」「たいそう」など)、叙述のしかたを修飾し、受ける語に一定の言い方を要求する陳述副詞(「あたかも」「決して」「もし」など)の3種に分類される。なお、程度副詞は、「もっと東」「すこしゆっくり」のように体言や他の副詞を修飾することもある。
【形容詞】
活用のある自立語で、文中において単独で述語になることができ、言い切りの形が口語では「い」、文語では「し」で終わるものをいう。「高い・高し」「うれしい・うれし」の類。事物の性質や状態などを表す語で、動詞・形容動詞とともに用言に属する。口語の形容詞は活用のしかたが「(かろ)・く(かっ)・い・い・けれ・〇」の一種であるが、文語の形容詞にはク活用・シク活用がある。
辞書、、、難しいですね。更に色々と調べてみると、やっと少しですが理解出来る記載がありました。
副詞は文の中でほかの言葉の意味を詳しく説明する語で、次のようなものがあります。「すっかり、ずっと、すやすやと」「いささか、いと、たいそう」「あたかも、決して、もし」になります。そして形容詞としては、次のようなものがあります。「 美しい、優しい、賢い、虚しい、怖い、痛い、悲しい、美味しい、醜い、悔しい、可愛い、 大きい、長い、若い、深い、遠い、暗い、薄い、古い、太い、新しい、明るい」になります。
理解出来たような、出来ていないような、、、やはり日本語は難しいですね!
副詞とは文章(言葉)自体?を修飾(しゅうしょく:美しく飾る事。意味を限定したり、詳しくしたりする事。)したり、詳しくしたりするもので、形容詞とは物(人)の状態を修飾したり、詳しくしたりするものとなるのでしょうか。小説家先生が話をされた言葉の意味は『修飾していない、現実の状態を明確に表現した文章が良い』という事だったのかもしれません。特に形容詞は「美しい、優しい、大きい、長い、遠い、新しい(抜粋)」といったように個人の感覚や基準によって理解が様々になる事が考えられます。そして状態を明確に正確に伝えるには語彙力や観察力も重要になってくるのかもしれません。
そうだとすれば、その副詞や形容詞を使わない文章が私には、、、なかなか作成出来ません。
本当に難しいですね。日々精進していこうと思います。
(私の学力や理解力では色々と間違っているかもしれません。勘違いや間違い等がある場合はお許しを頂ければ幸いです。)
長いようで短い1ヵ月。又1ヵ月後に更新致しますので、お付き合いを宜しくお願い致します。
社長だより vol.110
今年のGW(ゴールデンウィーク)は、4月30日から5月2日までの平日3日間に有給休暇を取得すると10連休になります。有給休暇を取得された方は、ゆっくり楽しんでリフレッシュをして頂ければと思います。又、業務の都合などでカレンダー通りに業務をこなしている方もいると思います。昨日からの3日間は、しっかり業務をこなして、その後の4連休を楽しんでリフレッシュしましょう。そしてどちらの方も連休明けには、気持ちを新たに日々の業務に邁進しましょう。
先月下旬にニュースで「全国の自治体の4割で2050年までに20代から30代の女性が半減し“最終的には消滅する可能性がある”」とした分析結果について報道されました。更には「秋田県内では秋田市を除くすべての市町村が“消滅可能性自治体”となっていて、“消滅可能性自治体”の割合は47都道府県で最も高い」との報道もありました。
私は“人口減少”や“少子高齢化”について、ある程度は理解や把握をしていたつもりでしたが、今回の報道には非常に驚きましたし、危機感を感じました。そして令和3年2月(2021年2月)の社長だよりで取り上げた「秋田県の現実・将来予測について『国立社会保障・人口問題研究所』が2017年に“将来推計人口”を予測算出していた事」について思い出し、再び現状と比較をしてみました。その際に活用したデータに現状を加えて下記に記します。

2017年に予測されたデータと2024年4月1日時点での実数を比較しています。(秋田県公式HPに記載のあったデータを引用しています。) 来年2025年の予測値と比較して大半の自治体で大きな差が生じていない事から、この予測が大袈裟ではない事が理解出来ます。
(2024年4月1日時点で既に2025年の人口予測を下回っている自治体が“2”あります。又、2020年予測より人口が増加している自治体が“1”あります。)
この予測から21年後の2045年には秋田県の人口が601,649人となる事は現実味を帯びています。そして2050年には秋田県内で秋田市以外が“消滅可能性自治体”だという事も同様です。
このデータや消滅可能性自治体について、皆さんは何を思い、何を考えましたか。
「予測は、あくまでも予測」とは言えないくらい、来年2025年の人口予測に大半の自治体では人口が近づいています。令和3年2月(2021年2月)の社長だよりにも記しましたが、一般的に人口減少が進めば税収は減り、地域経済も低迷する事が予測されます。又、少子高齢化が進めば労働力の確保が難しくなったり、必要とされる事業や業務にも変化が起こる事も予測されます。
自治体や各種団体が人口減少に歯止めをかけるべく、様々な取り組みを行なっている事は認識しています。しかし今回の報道(データ)も現時点での“事実”になります。しかしその事実の中に1つだけ嬉しい出来事「2020年予測より人口が増加している自治体“1”」がありました。これは救いの神と思い調べてみると「ダム建設に伴う、作業員らの移住によるもの。大規模な事業によって一時的にプラスになったに過ぎない。」との事でした。非常に残念です。
今回は“消滅可能性自治体”や“人口減少”“少子高齢化”をしっかりと理解する(理解を深める)為に再び自治体別人口予想データと現在の秋田県及び各市町村の人口を皆さんにご紹介しました。私は現実的に直面している事実について、理解を深める事が出来ました。そして理解は深まりましたが、自分自身が人口減少に歯止めをかける為に何をやるべきか、、、
考えてみた結果、正解は分かりませんが1人でも多くの若者が秋田県内で生活しようと思えるように、秋田の魅力を再確認して「秋田での生活が楽しい!」「秋田にも素敵なもの(こと)が沢山ある!」「秋田の〇〇は最高!!!」と胸を張って笑顔で発信していこうと強く思いました。
現在、秋田に住んで生活している皆さん!、、、「秋田、悪くないですよね!!!」。
長いようで短い1ヵ月。又1ヵ月後に更新致しますので、お付き合いを宜しくお願い致します。
社長だより vol.109
今日から新年度、令和6年度がスタートとなります。皆様、新年度も何卒宜しくお願い致します。そして4月は新たな出会いの多い時期になりますね。業務上でも普段の生活でも新たな出会いには楽しみだけでなく不安を抱える方も少なくはないと思います。しかし新たな出会いには思いがけない気付きも多く含まれると考えられますので、是非ともポジティブに捉えて新たな出会いを“楽しんで”日々の活動や生活を送って下さい。
出会いは、普通に考えれば初対面になると思います。そして初対面で相手の情報が何もないとき、最初に目にするのは「顔/身なり」です。「人は見た目が9割」などと言われるように、最初に抱いた印象が、その後の対応に影響してしまうと言われています。“顔”は別として“身なり”は日頃から気を付ければ何とかなります。(身なりについて私も日々“TPO”に気配りしているつもりですが、、、)
そして、その印象を確定させたり、変化させたりするのが「言葉(会話力)」だと思います。私は今まで“社長だより”で“語彙力”について5回ほど掲載しましたが、未だに自身の語彙力(言葉/会話力)の無さを感じながら日々精進しています。
今回はその「言葉/会話力」に関連した「敬語」について、最近読んだ雑誌の中にあったコラム「“デキる!”と思わせる敬語の使い方」の中から以下に少しだけご紹介致します。
【以下、記事の抜粋になります】
敬語は難しいと、多くの人が感じるのは何故でしょうか。敬語は、距離感を置くことによって相手への配慮や敬意を伝える言語的な「道具」です。適切な敬語とは、不動の正解といえるような型があるわけではありません。相手と自分の関係性(上下関係や親疎関係)や状況に応じて、ふさわしい敬語を柔軟に選ぶ必要があります。敬語には従来の尊敬語、謙譲語、丁寧語に丁重語、美化語が加わり合計5種類あり、改まり方の度合い(丁寧度のレベル)も多様です。しかも相手、状況、トピックによってふさわしい敬語の種類を、その場その場でチョイスして使わなければなりません。難しいと感じるのも当然です。( ~ 中略 ~ )
『言葉は生もの、絶対の正解はない』
敬語を「使われる側」のときについて考えてみましょう。部下から「この本、拝読してもらえますか。」などと謙譲語を使われたり、それほど親しくないと思っている人から「あ、どうも。久しぶり。」とタメ語を使われると、不愉快になることはありませんか。
そこで私からの提案です。敬語の失敗に対して、太っ腹な気持ちで接してみては如何でしょうか。たとえ尊敬語を使うべきシーンで間違って謙譲語を使われたとしても、敬語を使おうとしている時点で「この人は私に敬意を示したいのだな。」とわかるはずです。タメ語を使われたときは「この人は、自分と親しくなりたいと思っているんだな。」と考えればよいと思います。
言葉は大事ですが、もっと大事なのは相手の気持ちです。この言葉によって何を伝えたいのか、バカにしているのか、敬意を示したいのかはすぐにわかるはずです。言葉は発するほうの配慮も大切ですが、受け取る側が相手の意図を汲む姿勢も大切です。
敬語に絶対の正解はありません。少し前まで正しいとされて言葉も、時代によって変わっていくからです。
今回ご紹介した「敬語」について、皆さんは何を思いましたか。私はまず「敬語」が尊敬語、謙譲語、丁寧語だけでなく、丁重語(ていちょうご)、美化語(びかご)を加えた合計5種類ある事を知りませんでした。因みに「丁重語」とは、自分の行為などを相手に丁重(礼儀正しく、手厚いこと)に述べる言い方になり、「美化語」とは、物事をきれいに(上品に)いう言い方になるそうです。
そして私も「敬語は難しい」と感じている1人です。難しいと感じている理由は、5種類の敬語(情けないですが、今回コラムを読むまでは3種類だと思っていました、、、)の区別も曖昧で正しい使い方も理解していないからだと考えます。本当に“語彙力”や“言葉/会話力”の無さを痛感します。
しかし今回ご紹介したコラムでは「敬語に絶対の正解はない」「大事なのは気持ち」と書かれてあります。ここは得意のポジティブシンキングで、間違いがあっても良いから気持ちを込めて敬意を示していこうと強く思いました。又、敬語に限らず「受け取る側が相手の意図を汲む姿勢も大切」との考え方も頭の中に入れて、業務や日々の生活を送ろうと思います。
長いようで短い1ヵ月。又1ヵ月後に更新致しますので、お付き合いを宜しくお願い致します。
社長だより vol.108
気が付けば、もう3月です。今年の冬は本当に積雪が少ないというか、ありませんでしたね。(まだ冬は終わっていませんね・・・) 先月2月には、その日の最高気温が平年5月上旬並みとなる暖かい日もあったかと思えば、急に雪が降り積もる日があったりもしました。まだまだ寒さを感じる事は少なくはありません。寒暖差により体調を崩す事がありますので、体調管理には十分に注意して日々お過ごし下さい。
今回はあるビジネス誌で掲載されていた『プレッシャーに弱い人は、なぜ弱いのか』というコラムについて、少しご紹介したいと思います。コラムの冒頭で「大切な大舞台、“落ち着け”“集中しろ”と念じるほど、焦りを生んで失敗してしまう・・・。多くの人は、そのミスの原因を精神面に求めがちです。」との記載があり、自分自身に重ねても“その通りだな”と感じてしまいました。しかし読み進めていくと「スポーツであれ仕事であれ、その場その場で行なうべき動作や作業の基本が身に付いていなければ、環境が少し変わっただけでも動揺して、良いパフォーマンスが望めなくなる、という事だと思います。」との記載がありました。ここでは更に精神ではなく、基本が大切だと改めて痛感させられました。その後、読み進めていくとプレッシャーに打ち勝つための“集中力とは”との記載がありましたので、以下に記します。
【集中力とは、注意力を目的に注ぎ込める力】
スポーツ心理学者の市村操一先生によると、心理学では集中力の中身は「注意力」と考えられているそうです。いわゆる集中力は、注意力をタイムリーに、しっかりと目的に向けて注ぎ込む力を指すのです。そして、人間が本当に集中力を発揮出来る時間は、1日のうちで合計40分程しかないそうです。また、人間が一定時間内に使える注意力のキャパは限られていると言われています。
人間のメンタルは大きく2つに分けられるようです。1つは「認知」。状況判断や思考、意思決定などです。もう1つは「感情」。不安やイライラなどです。例えばゴルフでは、プレッシャーを感じると認知力が落ち、感情が揺らぐため自己認識がうまく出来なくなり、悲観的になったり不安になったりします。日常生活も同様です。そんな時は無理にプレッシャーを打ち消そうとしてもうまくいきません。緊張でドキドキしているときは、心を何とかしようとか、無理にいじろうとするのではなく、ここで何をすべきかを思い出して、それを履行することです。
人生の進路を決定づける大事な試験や大きな仕事のプレゼンをするような場で、緊張で頭が真っ白になり、何をやっていいか分からなくなりドキドキする状態になったら、まずは息を大きく吐くと身体の力が抜けます。基本に立ち戻り、何をやるべきか、どう動くべきかを思い出し、自分はこれだけ押さえれば、ちゃんと出来るんだと確信を持ってやりとげるのです。
その場で自分がやるべき最も基本的なことを徹底的に単純化して現実の行動に落とし込み、それを身に付けておけば、緊張を誣いられる場面でも本来の力量に見合ったパフォーマンスを発揮出来るようになるのではないでしょうか。
集中力について皆さんは何を考え、何を思いましたか。私自身はプレッシャーに弱い方だと感じています。言葉では「なるようにしかならない!」と発して、心の中では「どうしよう、困ったな、まずいな・・・」と思う事が多々あります。しかしそれは今回のコラムから“基本が身に付いていない”“基本的なことを徹底的に単純化して現実の行動に落とし込んでいない”からだと理解出来ました。やはり何事も“基本”が大事ですね。遅いかもしれませんが、これからは基本が身に付くように日々努力し、徹底的に単純化して行動に落とし込めるまで考えていこうと感じました。又、人間が本当に集中力を発揮出来る時間は1日40分程しかないとの事ですから、集中するタイミングも選択して、より良いパフォーマンスを発揮しようとも思いました。
たとえ集中出来たとしても“本来の力量”しか発揮出来ません。しかし普段から努力を惜しまず本来の力を強化して、そして自分を信じて、ドキドキしたら息を大きく吐いて身体の力を抜いて、日々様々な事にチャレンジしていきたいと強く思いました。
長いようで短い1ヵ月。又1ヵ月後に更新致しますので、お付き合いを宜しくお願い致します。
社長だより vol.107
今年の冬は積雪が少ないですね。というか、ありませんね。しかし日によって、あるいは朝晩は流石に寒さを感じる事は少なくはありません。また積雪が少ないので車の運転も気を遣う事がなく、予期せぬ凍結路面で滑ってしまい“あっ!”と息を飲む瞬間があります。皆さんも時間に余裕をもって行動し、車間距離を十分に保ち、安全運転には注意して日々お過ごし下さい。
今回はあるビジネス誌で掲載されていた『“人を見る目”“人を見抜く力”は真剣に人と向き合う事で培われる』というコラムについて、ご紹介したいと思います。著者は銀座の地で開店40周年を迎えたオーナーママさんで“コミュニケーションのプロ”“おもてなしのプロ”“人間観察のプロ”と言われている方です。コラムを読んで、私が特に考えさせられた部分を以下に抜粋にて記します。
【目は口ほどにものを言う~第一印象では、目を見ます】
「人を見る目」「人を見抜く力」についていえば、一朝一夕で身につくものではなく、真剣に人と向き合うことの積み重ねによって培われていくもののように思います。短時間で「人となり」を見抜くことは難しいものです。とはいえ、面接では短時間で判断しなければなりませんので、まず目を見ます。「目は口ほどにものを言う」が如く、心は目に現れます。目を見れば、人から好かれているかがわかります。清潔感や会話の中からにじみ出る人間性もよく見ます。顔つきや表情、かわいげのある人には心が動くものです。また相手の目を見て話ができるというのも人に対する誠実さが表れます。逆に、ソワソワしたり、すぐに目をそらしたりするのは、あまりいい印象を与えないように思います。
(~ 中略 ~)
大事なのは、言葉遣いや気遣いといった人に対する礼節です。これは接客に限らず、どんな職種でも必要なヒューマンスキルではないかと思います。もちろん完璧な人などいませんから、アドバイスされたら直していく、そのように人の言葉を素直に聞き入れる柔軟な心を持っている人は、どこにあっても歓迎されるのではないでしょうか。
【高い目標を持つと同時に成し遂げるための努力に目を向けられるか】
高い目標を持ち、目指すものに向かって、努力研鑽を重ねていくのは素晴らしいことです。ところが意気揚々と目標を話すわりに「では、どうやったらナンバーワンになれると思いますか」と尋ねると黙ってしまう、具体的に何をするか答えられないというケースが少なくありません。最初から頂点、「成功」という表側だけを見て、見えない部分の努力を想像できない人は成功にたどり着くのは難しいように思います。どの世界でもトップになる人は水面下での真剣な努力があっての成功であり、それこそが肝心であって、すべてともいえます。
(~ 中略 ~)
皆様もご存じのように、仕事においては、時に窮地に追い込まれたり、裏切りにあったり、いいことばかりではありませんが、何があろうと、逃げずに、辛抱強く、諦めず前に進む、それが「真剣」に生きることではないでしょうか。
当たり前といえば当たり前な事ですが、皆さんは何を考えましたか。私は文中に何度か出てくる「真剣」という言葉について考えさせられました。因みに「真剣」を調べてみると『本気で物事に取り組むさま。真面目に物事に対するさま。』という意味でした。自分は物事に対して、どれだけ“本気で”“真面目に”取り組んでいるかを思い出すと、、、。また目標を達成する為の方法や手段をどれだけ具体的に話せるかを考えると、、、。なんだか情けない気持ちでいっぱいです。
これからは、どんな事にも“真剣”に向き合って取り組んでいこう、1つ1つの目標を達成する為の方法や手段も“真剣”に考えて語源化出来るようにしていこう、更には人の言葉を素直に聞き入れる柔軟な心を持ち続けようと強く思いました。(例えば会食(飲み会)の場においても“礼節”を忘れず人の話に耳を傾けて“真剣”に取り組んでいきたいと思います。)
長いようで短い1ヵ月。又1ヵ月後に更新致しますので、お付き合いを宜しくお願い致します。
社長だより vol.106
謹んで新春のお慶びを申し上げます。本年も良い年になりますように心からお祈り致します。
令和6年(2024年)も何卒宜しくお願い致します。今年は「辰(たつ)年」になります。漢字の「辰」は「振るう」という文字に由来しており、自然万物が振動し、草木が成長して活力が旺盛になる状態を表すそうです。「辰」は「竜(龍)」のことでもあり、干支の中で唯一の想像上の動物になります。理由は分かっていませんが「本来干支の各文字には動物は関係なかったのに、あとから同音の動物を紐づけたせいで想像上の動物が入ってしまった」という説や「龍という字に鰐(ワニ)の意味もあったので、そもそもは龍ではなく鰐(ワニ)を指していた」とする説があるそうです。(西アジアや東ヨーロッパの一部にも十二支の風習があり、アラビアでは“辰”が“鰐(ワニ)”に置き換わっており、イランでは“辰”が“鯨(クジラ)”に置き換わっているそうです。)
又、「竜」は古来より権力や正義の象徴とされ、縁起の良い生き物とされています。更に古くから「竜王」「竜宮の神」「竜宮様」とも呼ばれ、水を司る水神として日本各地に祭られています。神社などの手水舎(水盤舎)で竜が口から水を吐き出しているのは、まさに水にまつわる神ならではです。
昨年も紹介しましたが、株式相場には【辰巳天井、午尻下がり、未辛抱、申酉騒ぐ、戌は笑い、亥固まる、子は繁栄、丑はつまずき、寅千里を走り、卯は跳ねる。】という格言があるそうです。景気が良くなり“辰巳天井”の字のごとく“高値安定”となる事を切に願っています。又、他に【戌亥の借金、辰巳で返せ】という格言もあるそうです。戌年や亥年は株価が下がり、辰年・巳年は株価が上がりやすいので、戌亥年で出来た借金も、辰巳年で取り返せるという意味だそうです。どちらにしても株式市場にとっては縁起の良い年として知られています。
「十二支(じゅうにし)」」と「十干(じっかん)」を組み合わせた、本来の「干支六十干支(ろくじっかんし)」では2024年の辰年は「甲辰(きのえたつ)」となり、順序で言えば41番目になります。「甲(きのえ)」は十干の始まりにあたり、生命や物事の始まりを意味しているそうです。冒頭に記した「辰年」の意味「自然万物が振動し、草木が成長して活力が旺盛になる状態」と合わせて、更なる成長をする年になる事を願って日々努力していこうと思います。
色々調べてみると2024年も良い年になりそうですね。実は私は年男になります。天高くのぼる竜のごとく成長する為に活力が旺盛な状態を保ちつつ、今まで以上に新しい事にチャレンジして、自分自身の力で良い年にしようと思います。
(関連?した事で、、、)
名前に「龍」の文字が入る有名人といえば、幕末の志士『坂本龍馬』がいます。龍馬をここまで有名人にしたのは、司馬遼太郎さんの歴史小説『竜馬がゆく』だと言われています。
あれ?『龍馬?』『竜馬?』どちらが正しいのでしょうか?
高知県立坂本龍馬記念館によると、龍馬本人は一度も『竜馬』と書いたことはないそうです。司馬遼太郎さんが小説の中で独自のリョウマを描く為に、あえて龍馬の文字を使わなかったとも言われているそうです。どちらにしても格好良い名前ですよね!!!
長いようで短い1ヵ月。又1ヵ月後に更新致しますので、お付き合いを宜しくお願い致します。
令和6年1月
社長だより vol.105
早いもので2023年も残り1ヵ月となりました。2020年から続く“新型コロナウイルス”の感染症分類が今年5月に2類相当から5類に引き下げとなり、様々な制限や我慢、困難や努力から解放された生活を今は送れています。しかし新型コロナウイルス感染は終息した訳ではありませんし、季節性インフルエンザの感染が増加傾向にあります。又、お酒を嗜む機会が増える時期でもあります。体調管理には十分に気を付けて、日々を楽しく過ごしていきましょう。
今月は最近読んだ雑誌に掲載されていた『AI時代だからこそ問われる、「雑談」の真価とは』というコラムについてご紹介したいと思います。以下に抜粋を記します。
人工知能がますます発達して、人間の仕事のあり方も変わろうとしている。最近ある人に聞いた話では、子供達の一部で「悲観論」が流行っているという。「これからは全部人工知能がやってしまうから、ぼくたちがやることはないよね」と子供達がお互いに言っているのだという。子供の考え方というのは、いつの時代も大人達の気分を反映する。( ~中略~ )
しかし悲観する必要はない。人工知能がどれほど発達しても、社会や経済のあり方が大きく変化しても、新しい局面を切り開いていく人間の能力が不必要になる事はないのだ。むしろ、私達は時代に合わせて自分達の能力を磨いていったらよい。
ところで、ある人の能力がどの程度のものか、また仕事がどれくらい出来るかが分かる一番のテストはなんだろうか?ずばり、それは「雑談」である。たかが雑談、されど雑談。雑談をないがしろにする人は仕事が出来ないし、人に信頼されないし、何よりも自分の人生の可能性を十分に活かす事出来ないのである。なぜ仕事が出来る人は雑談力が高いのか?雑談には、人間の能力の本質に関わる判断し選択する能力や、相手に信頼されて共同作業の礎を築く能力が反映されるからだ。
雑談には、その人の全てが表れる。大脳皮質の側頭連合野に記憶された様々な知識、人生経験、人間観、気遣い、大局観などが言葉を通して明らかにされる。相手の話を聞き、自分が話す「話者交代」をどれだけ的確に出来るかも問われる。
(ちなみに、、、)
今回も“雑談” をウィキペディアで調べてみると「特にテーマを定めないで気楽に会話する事。一般的に、とりとめのない話である事が多い。」とありました。
“気楽”で“とりとめのない”ような事が、、、“ないがしろ“にしてはいけない“大切”な事なのですね。
今回、抜粋ではありますがご紹介したコラムを読んで皆さんは何を思い、何を考えましたか?私は「子供の考え方というのは、いつの時代も大人達の気分を反映する。」との言葉について非常に考えさせられました。コラム内の言葉は、世の中全体に対しての言葉だとは思います。私は非常に身近な事になりますが、自分自身の子供達にどのような気分で接してきたのか、どのような考え方を伝えてきたのか、しっかりと思い出す事が出来ません。親として一番近くにいる大人として、恥ずる事無い対応が出来ていたかは疑問ですが、もう既に子供達も大人です。今度、帰秋した際にはじっくり話をしてみようと思います。それこそ“雑談”してみます。
また様々な知識、人生経験、人間観、気遣い、大局観などが言葉を通して明らかになる雑談です。普段の自分がどのような雑談をしているかが気になりました。どちらかと言えばウィキペディア調べの“気楽”で“とりとめのない”話をしていたように思います。今後は雑談であっても大切にして、相手の話も聞きながら、AIには絶対に出来ない血の通った会話“雑談”をしていこうと心に強く思いました。そして今更かもしれませんが、、、仕事が出来る、信頼される人間を目指します!!!
長いようで短い1ヵ月。又1ヵ月後に更新致しますので、お付き合いを宜しくお願い致します。
令和5年12月
社長だより vol.104
今年は熊の“目撃”“遭遇”そして“被害”が過去最多となっています。山林での目撃や農作物への被害だけではなく、市街地で人に対しての被害も非常に多く報告されています。共生は難しい事なので、まずは遭遇しないよう自身の存在に気付いてもらえるような行動を心掛けましょう。
先日「夢が自分を育てる」という講演をお聞きしました。秋田県野球界にご尽力をされた方で、ご自身の体験や高校野球・プロ野球選手などの夢や行動を交えてのお話にあっという間の1時間でした。今回はその講演でお聞きした“夢”に関する事を2つご紹介致します。
●日本と欧米の“夢”に対する認識の違い
欧米では“夢”は“叶うもの”“強く願えば現実になるもの”と認識されています。そして「夢が見つかったなんて、凄いじゃないか」と言ってくれる人が多数だそうです。
一方、日本では“夢”は“儚いこと”“頼りにならないこと”“現実から離れた甘い考え”などと認識されています。そして周囲の人には「夢みたいな事ばっかり言ってないで〇〇しなさい」などと言われてしまいます。
(ちなみに、、、)
“夢”をウィキペディアで調べてみると「睡眠中あたかも現実の経験であるかのように感じる、一連の観念や心像のこと。睡眠中にもつ幻覚のこと。」とありました。
その通りだとは思いますが、、、なんだか“夢”がないですね。
●夢七訓
夢なき者は 理想なし 理想なき者は 信念なし 信念なき者は 計画なし
計画なき者は 実行なし 実行なき者は 成果なし 成果なき者は 幸福なし
ゆえに幸福を求むる者は 夢なかるべからず
開国から昭和初期までの激動の時代において、日本経済の基礎を築き、日本初の銀行を設立しただけでなく、様々な種類の会社設立にも携わった日本資本主義の父とも言われる渋沢栄一さんの言葉です。夢を持つことの大切さが語られています。
(渋沢栄一さんは2024年から使用される新一万円札の顔になる予定です。)
皆さんは“夢”について、どのように考えますか。認識について私は、欧米の夢に対する認識が凄く好きです。いわゆる「ポジティブシンキング!」ですよね。そして日本の認識が“儚いこと”“頼りにならないこと”“現実から離れた甘い考え”との説明に少し違和感を覚えました。時と場合によっては、そのように考える事もあるかもしれませんが、全てではないと思っています。
誰でも叶えたい“夢”はあるはずです。勿論、私にもあります。その夢を強く願って現実にしていく為に渋沢栄一さんの“夢七訓”を心に秘めていきたいと強く思いました。
(余談になりますが、、、)
講演の冒頭で「皆さん、小学校の卒業文集に自分の夢を書きましたか。書いた人は内容を覚えていますか。」と問われました。私は正直、書いたかどうかすら覚えていませんでした。しかし、その際に10年以上前の長男の卒業式を思い出しました。小学校が小規模でしたので、一人ひとりステージに上がって卒業証書を頂き、その後「私の夢は〇〇になる事です。」と大きな声で発表してステージを下りるスタイルの卒業式でした。長男の発表した夢、、、途中で変わったようです。
又、その時私はPTA会長でしたので祝辞を行なわせて頂きました。その内容の一部が「夢を叶える方法を1つ紹介します。皆さんの夢に期限を設定して下さい。その瞬間に夢は目標に変わります。そしてその目標と今の自分を比べて足りない事をどのように埋めていくかを考えて下さい。それが計画です。計画した事を日々実行する事により目標つまりは夢が叶います。」でした。なんだか渋沢栄一さんの“夢七訓”に少しだけ似ているような気がします。気のせいですかね。
長いようで短い1ヵ月。又1ヵ月後に更新致しますので、お付き合いを宜しくお願い致します。
令和5年11月
社長だより vol.103
今年の夏は非常に暑い日が続きました。9月中旬まで最高気温が30℃を超える日もありましたが、今は秋らしい朝晩涼しい日々となっています。秋は過ごしやすく、収穫の時期でもある事から「スポーツの秋」や「食欲の秋」など様々な楽しみがあります。皆さんも沢山の「〇〇の秋」を堪能しながら、体調管理には十分に気をつけて日々をお過ごし下さい。
私だけでなく皆さんも日々、体調管理いわゆる健康には十分に注意していると思います。そして毎年、健康診断を受診しているはずです。私も先月、健康診断を受診しまして数日前に結果が送付されてきました。結果は、、、決して誇れる内容ではありませんでした。(飲み過ぎ注意!!!)
そんな最近、ある雑誌を読んでいると『健康診断のウラ側!知らなきゃ大損!』のタイトルを目にし読み進めていくと、驚く内容が記されていましたので、以下に抜粋して紹介します。
『健康診断は受けてもほとんど意味がない』
日本ほど健康診断への信仰が篤い国も、ほかにないでしょう。健康診断が寿命を延ばすというエビデンスはどこにもありません。だから世界を見渡すと日本や韓国を除くほとんどの国では、健康診断を強制していないのです。日本の健康診断で示される「判定」の多くは統計的なものです。健康と考えられる現役世代の人の平均値を挟んで、95%の人を「正常」、そこから外れた5%の人を「異常」と呼び、数値の判定が直接的に健康かどうかを示してくれるわけではないのです。ですから、異常値でも健康な人がいれば、正常値なのに疾患を持つ人もいます。(~中略~)
2019年に、過去の研究データをすべてまとめた論文が発表されました。その中で健康診断を行なった人と行なわかった人で、病気による死亡率に差がつくかどうかを検証しています。論文の要旨にはたった一行こう記されています。
≪全体的な健康チェックが有益である可能性は低い≫
この結論は、健康診断を行なった結果、ガンによる死亡率、あるいは心筋梗塞や脳卒中による死亡率が下がっていないというエビデンスに基づいています。それは、健康診断で治療できる病気が都合よく見つかる可能性は極めて低いからです。
『医者が勧める禁煙・禁酒は倫理的に問題あり』
医者が健康の為だからといって患者さんに「生活の楽しみをガマンしなさい」と言って、食事制限を課したり、好きでもない運動を強いたりするのは、倫理的な問題です。まさに禁酒や禁煙がそうです。患者さんに「タバコを吸ってもいいですか?」「お酒を飲んでもいいですか?」と聞かれれば、医者としては「やめたほうがいいですよ」と答えざるをえません。どちらも体に悪いことは明らかですから。(~中略~)
医者の立場から言えば、減塩や運動、禁酒、禁煙など生活習慣に関するアドバイスは便利です。効果があってもなくても責任をとらずにすむからです。
この他にも「我慢しない生活はよい人生への近道」「減塩しても脳卒中や心筋梗塞の予防効果はない」「瘦せるために運動しても徒労に終わる」など様々なサブタイトルで健康不安に陥らない為の考え方が紹介されていました。私が都合よく抜粋している訳ではありませんので、興味を持たれた人は「PRESIDENT~2023.10.13号」をご確認下さい。
私が抜粋して紹介した内容を皆さんはどう考えますか。私は意外と健康診断の結果で一喜一憂するタイプです。(今回は、、、一憂でした。) 行動が伴っていないかもしれませんが、今回紹介した考え方とは逆で結果を真剣に捉えて、自分自身の日々の行動を考えます。しかし今回紹介した考え方が間違っているとは思いません。そういう事実や考え方もあるんだなと納得感もあります。
つまりこれがダイバーシティ(多様性)に繋がるんだと思いました。ダイバーシティ(多様性)とは多種多様な考え方があるだけではなく、お互いの考え方を認め合い、尊重し合う事が重要です。従って今回の場合は、仮に健康診断は有益でない事であっても、自分自身の健康を考えるタイミングと捉えて続けていこうと思います。
(現在も日本では、企業が「労働安全衛生法第66条」に基づき、医師による健康診断を従業員に受診させなくてはなりません。)
今回は健康診断についての考え方でしたが、日々生活していると様々なタイミングで違う考え方の人と話をする事があると思います。その際は是非“ダイバーシティ(多様性)”の考え方を思い出して、ただ話をする、聞くじゃなくて、認め合い尊重し合う事を心掛けていこうと改めて思いました。
長いようで短い1ヵ月。又1ヵ月後に更新致しますので、お付き合いを宜しくお願い致します。
令和5年10月
社長だより vol.102
毎日暑い日が続いていますが、今年は特に暑い日が多いように感じます。本日9月1日の秋田市は最高気温が34℃(最低気温25℃)との予報です。昨年9月1日の秋田市の最高気温を調べてみると22.9℃(最低気温20.6℃)でした。この事実からしても、やはり今年は異常なくらい暑いです。そしてまだ最高気温が30℃を超える日が続くようです。水分補給をしっかり行ない、体調管理には十分に気をつけて日々をお過ごし下さい。
今年6月の「社長だよりvol.99」で元WBC日本代表監督の栗山英樹さんについて記載させて頂きましたが、その際には著作「栗山ノート」で取り上げられていた言葉をご紹介しました。謙虚で視野が広く、日々努力を惜しまない栗山英樹さんについては、様々なメディアや雑誌で言葉や記事を目にする機会があります。今回は最近読んだ雑誌で取り上げられていた栗山英樹さんの「自分を育てる言葉」を抜粋してご紹介したいと思います。
●他人との比較を絶つ
SNSの発達で、様々なカテゴリで活躍する同年代のスタープレイヤーを容易に認知できるようになりました。しかし、そういった人と自分を比較して、劣等感を抱く必要は皆無です。それよりも、比較相手にするべきは過去の自分。昨日より今日、今日よりも明日と、着実に成長していくことのほうが遥かに尊い営みです。
●自分=組織という意識を持つ
当事者意識を持つことは、とても大事です。たとえば、平社員から社長までの全員が「自分の活躍が会社の存亡に直結する」と考えている会社は、組織として強いですよね。自分本位ではなく、組織を活かすためにはどうすればよいのか。この意識が根付けば、人として成長することができるでしょう。
●「自分は正しい」は禁物だ
見聞きした情報や自身の成功体験を、絶対的な「正しい答え」としてしまうと、視野狭窄に陥って他人の意見を聞き入れることができなくなります。あなたが正しいと信じることは、数ある選択肢のうちの1つにすぎません。もっとほかに、いいやり方あるかもしれません。「自分は正しい」という考え方は捨てましょう。
●基本、後輩のほうが優秀である
会社やサークルで、自分の後輩が著しく活躍して台頭したとします。危機感を覚える必要は、全くありません。人類は絶えず進化しているので、自分よりも後に生まれてくる人が優秀なのは当然なのです。そこで腐らず、自分にしかできないこと、自分ならではの強みを発揮し続けることができれば、評価は後からついてくるでしょう。
栗山英樹さんの「自分を育てる言葉」を読んでみて、皆さんはどう思いましたか。私は特に「他人との比較を絶つ」について、雑誌の中で『人間が変な悩み方をするときは、9割方、自分と他人との比較が原因です。(中略) 成長に必要なのは、他人と比較することではなく、自分が何をするかです。』との説明を読んで感銘を受けました。又、「基本、後輩の方が優秀である」についても『人類は絶えず進化しているので、自分よりも後に生まれてくる人が優秀』との説明が妙に納得出来ます。栗山英樹さんの言葉が「非常に分かりやく、心に響く」と思ったのは私だけではないはずです。全ての言葉が何かしら思い当たる事があったり、考えさせられたりします。
過去に6回ほど社長だよりで取り上げさせて頂いた“語彙力”も必要な事ではありますが、栗山英樹さんのように“分かりやすく、心に響く言葉や考え方”も大切ですね。これからも栗山英樹さんに注目していきたいと思います。
(実は、、、「栗山ノート2」が今年7月30日に発売され、既に購入しました。)
長いようで短い1ヵ月。又1ヵ月後に更新致しますので、お付き合いを宜しくお願い致します。
令和5年9月
社長だより vol.101
まず初めに先月7月14日から16日かけての想像を絶する豪雨により、秋田市を含む秋田県内各所や他県で浸水などの被害に遭われた皆様に心よりお見舞いを申し上げます。被災からの1日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。
そして自然災害はいつ発生するか分かりませんし、一度発生したら二度と発生しないという性質のものではありません。更に近年は「過去に類を見ない」「想像を超える(絶する)」自然災害が数多く発生しています。是非とも“過去”や“経験”に固執せずに、常に早めの対応や避難を心掛けて日々の生活を送っていきましょう。
私が色々と読んでいる雑誌の1つに『Wedge(ウエッジ)』というビジネス・情報誌があります。政治や経済などの話題が主となっていますが、その中に私が楽しみしている『拝啓オヤジ』というコラムがあります。毎回、息子・娘からオヤジへの手紙という形で日常生活の中の出来事から、何かに気付いたり、学んだりした事が記されています。1ページの読み切りで読みやすく、なかなか考えさせられる内容となっていますので、是非皆さんも機会があればご覧になって下さい。
今回は今月の『拝啓オヤジ』で人間偏差値を高める為に取り上げられていた『宝塚歌劇団のブス(ブオトコ)の25ヵ条』についてご紹介したいと思います。“清く、正しく、美しく”をモットーとする宝塚歌劇団に、昔ある日突然貼り出された25の戒めで“いつ、誰が、何のために張ったのか”が謎で、今はもうないそうです。その『ブス(ブオトコ)の25ヵ条』を以下に記します。
【ブス(ブオトコ)の25ヵ条】
●笑顔がない ●お礼を言わない ●おいしいと言わない ●目が輝いていない
●精気がない ●いつも口がへの字の形をしている ●自身がない
●希望や信念がない ●自分がブス(ブオトコ)である事を知らない
●声が小さくイジけている ●自分が最も正しいと信じ込んでいる
●グチをこぼす ●他人をうらむ ●責任転嫁がうまい
●いつも周囲が悪いと思っている ●他人にシットする ●他人につくさない
●他人を信じない ●謙虚さがなくゴウマンである
●他人のアドバイスや忠告を受け入れない ●なんでもないことにキズつく
●悲観的に物事を考える ●問題意識を持っていない
●存在自体が周囲を暗くする ●人生においても仕事においても意欲がない
この『ブス(ブオトコ)の25ヵ条』は、簡単に言えば「嫌われる人間のパターン」や「人間のあるべき姿を逆説的に示したもの」になると思いますが、皆さんはこれを読んでどう思いましたか。ご存じの方もいたかもしれませんが、私は初めて知りました。そして私は「やばい!当てはまるのがいくつかある!」と思うのと同時に“悲観的”には考えず「これから注意していこう!」と考えました。
(25ヵ条の1つ“悲観的に物事を考える”の逆を実践しました。)
誰でも“嫌われる人間”にはなりたくないと思います。“好かれる人間”とまではいかなくとも“少しでも魅力的な人間”を目指して『ブス(ブオトコ)の25ヵ条』と自分を比較出来た今回をチャンスと考えました。(ポジティブシンキング!大切ですよね!)
そして最終的には、継続する事も重要です。意識し続ける事で必然的に人間偏差値を高める事に繋がると思います。やっぱり『継続は力なり』ですよね。
長いようで短い1ヵ月。又1ヵ月後に更新致しますので、お付き合いを宜しくお願い致します。
令和5年8月
社長だより vol.100
6月11日に“梅雨入り”した秋田県ですが、ずっと夏のような暑い日が続き、直近の1週間ぐらいがジメジメした“梅雨”を感じさせる天候となっています。全国的には沖縄や奄美など、既に梅雨明けした地域もありますが、秋田県を含む東北北部の平年の梅雨明けを調べてみると「7月28日頃」でした。今年は全国的に梅雨入りが早かったので、梅雨明けも早まって欲しいと願っています。
(先月の社長だより冒頭で“梅雨入り”について記載しましたので、今月は“梅雨明け”です。)
今月は最近読んだ雑誌で特集していた『頭がいい話し方~できる!と思われる“大人の語彙力”』についてご紹介したいと思います。私が今まで“語彙力”について何度もご紹介しているので「あれっ?また?」と思われた方もいると思います。 (実は今回で6回目のご紹介になります。) しかし、毎回同じ雑誌や特集からご紹介している訳ではありません。つまり、それだけ世の中で注目されている、関心が持たれている事柄だという事ではないでしょうか。勿論、私も関心があり、常に意識しているつもりです。今回はその中から特に「好印象を与える“良質(丁寧)な表現”」について以下に少しだけご紹介致します。
【以下、記事の抜粋になります。】
初めて話した人でも、その人がどんな言葉を使っているかを聞けば、なんとなくその人のキャラクターをうかがい知る事が出来ます。言葉の選び方が上手で、表現力が豊かな人は、自身を持って意見を言ったり、相手の心を打ち解けさせることが出来ます。とはいえ賢く見られたいが為に、難解な表現やカタカナ言葉を乱用するのは逆効果です。「この人、何を言っているのか分からない」と、悪い印象を与えかねません。自分の伝えたい事が正しく伝わっているか、常に考えながら話すと良いでしょう。
①「 久しぶりですね。 」 良質(丁寧)な表現⇒ 「 ご無沙汰しています。 」
【解説】
「沙汰」は連絡、報告、知らせという意味を持ちます。久しぶりに会ったり、連絡を取ったりする際に使える表現です。
②「 元気ですか? 」 良質(丁寧)な表現⇒ 「 お変わりありませんか? 」
【解説】
相手の身の上や健康状態などに変化がないか気にかける時に使えます。「元気?」とカジュアルに聞くよりも丁寧な印象を与えます。
③「 頑張って下さい。 」 良質(丁寧)な表現⇒ 「 ご活躍をお祈りしています。 」
【解説】
「頑張って」という言葉がカジュアルすぎると感じたら、この表現を活用しましょう。「ご活躍を祈念します」などでも良いでしょう。
④「 体にお気を付けて下さい。 」 良質(丁寧)な表現⇒ 「 ご自愛下さい。 」
【解説】
相手に、自身を労うようにと気遣う言葉です。自分自身を大切にし、健康や幸福を守るようにという意を込めて使用出来る言葉です。
⑤「 楽しみにしています。 」 良質(丁寧)な表現⇒ 「 心待ちにしております。 」
【解説】
心の中で待ち望んでいる事を表現する「心待ち」という言葉になります。再会を心から待ち望んでいる事を伝える事が出来ます。
今回、特集されていた良質で丁寧な表現の中から特に簡単で普段から耳にした事のあるものをご紹介致しました。皆さんの中には日頃から使用している人もいるかもしれませんが、今回ご紹介した5つの表現をどのように思いましたか?私は意味までは微妙ですが、今回ご紹介した良質で丁寧な表現を知ってはいました。しかし、普段から使用しているかと思い返せば、、、。以前にも記載しましたが“語彙力”を上げる為には「意識的なインプットとアウトプット」が重要になります。知っている(インプット)だけではダメで、意識的に使用(アウトプット)しなくては「できる!と思われる“大人”」にはなれません。これから会話やメールなどで意識的に使用して、最終的には無意識でも良質で丁寧な表現を使用出来る「できる!“大人”」を目指します。又、この“社長だより”が少しでも皆さんのインプットになれば有難いと思っています。
長いようで短い1ヵ月。又1ヵ月後に更新致しますので、お付き合いを宜しくお願い致します。
令和5年7月
社長だより vol.99
過ごしやすい気温の日々が続いていますが、6月と言えば“梅雨”です。全国的には既に梅雨入りした地方もあります。秋田県を含む東北北部の平年の梅雨入りを調べてみると「6月15日頃」でした。しかし既に梅雨入りした地方は全て“平年より7日前後早く”梅雨入りしています。今年の梅雨入りは早まる傾向のようです。秋田県も、もう少しで梅雨入りとなるかもしれませんね。
(ちなみに昨年、東北北部の梅雨入りは6月6日頃でした。)
今月は最近読んだ本『栗山ノート』についてご紹介したいと思います。勿論、皆さんご存じの「2023年WBC日本代表監督:栗山英樹さん」の著作です。2019年の10月に初版が発売されましたが、今回のWBCでの活躍が引き金となり再注目されています。私も再注目の波にのり、購入した1人になります。栗山英樹さんは幼少の頃から“野球ノート”をつけているそうで、学生時代やプロ野球選手時代、ジャーナリスト時代や監督時代と様々な立場でその時のプレーや思いだけでなく、古典や経営者の著作から抜き出した言葉などでノートは埋め尽くされているそうです。その“野球ノート”から抜粋したものが著作『栗山ノート』になります。
今回は『栗山ノート』で取り上げられていた“言葉”をご紹介致します。
●『五事を正す』
江戸時代初期の陽明学者で、近江聖人と称された中江藤樹(とうじゅ)は、人間として大切な道を学び、実行していきました。その教えのひとつで五事とは「貌(ぼう)、言(げん)、視(し)、聴(ちょう)、思(し)」を指します。「五事を正す」ことが、すなわち良知=美しい心を磨き、家族を大切にする、先祖を敬う、大自然の恵みに感謝することにつながります。
「貌(ぼう)」は風貌や容貌、美貌などの単語で使われ「なごやかな顔つき」を意味します。「言(げん)」は思いやりのある言葉で話しかける。「視(し)」は澄んだ目で物事を見つめる。「聴(ちょう)」は耳を傾けて人の話を聴く。「思(し)」はまごころを込めて相手のことを思う、という事です。
●「これを知る者は、これを好むに如(し)かず。これを好む者は、これを楽しむ者に如(し)かず」
「論語」の有名な言葉です。学ぶことにおいて、その知識を知っているということは、勉強を好きな人には及ばない。勉強を好きな人は、勉強を楽しんでいる人間には及ばない。知ることよりも好きなことが、好きなことよりも楽しむことが上達につながる、ということでしょう。
●「人生では批判する側ではなく、批判される側にいるべきだ」
脚本家の倉本聰さんが助言してくれた言葉です。批判される側は、何かを作ったり起こしたりする立場にあります。それに対して批判をする側は、作られたもの、起こったものに対して意見をする立場です。(こちらは本編ではなく、前書きで紹介されていた言葉になります。)
皆さん、今回ご紹介した3つの言葉について、何を思い、何を考えましたか。私は、まず栗山英樹さんが凄い勉強家で野球のことだけでなく、様々なジャンルを網羅している事に驚きを感じました。そして著作のあらゆる部分で「野球人としても、ひとりの人間としても、何ひとつ成し遂げていない自分が、、、」「私自身の能力が足りていない、、、」などといった言葉で“謙虚な気持ち”を感じる事が出来ました。やはり何かを成し得る人は、謙虚で視野が広くて日々努力を惜しまないのだと改めて気付かされました。又「なごやかな顔」「思いやりのある言葉」「澄んだ目」「耳を傾ける」「相手のことを思う」は非常に大切な事だと思います。人間誰しも気分が良い時だけではありませんが「五事を正す」を心掛けて、どんな時にも“楽しみながら”“謙虚な気持ちを忘れずに”何かを作ったり起こしたりしていきたいと思いました。
長いようで短い1ヵ月。又1ヵ月後に更新致しますので、お付き合いを宜しくお願い致します。
令和5年6月
社長だより vol.98
今日5月1日と明日2日に有給休暇を取得して9連休という方もいると思います。せっかくの機会ですから、充分に楽しんでリフレッシュをして頂ければと思います。又、業務上の都合などで普段通りお仕事をしている方もいると思います。今日と明日の2日間、しっかり仕事をこなして、その後の5連休を楽しんでリフレッシュしましょう。そしてどちらの方も連休明けには、気持ちを新たに日々の業務に邁進しましょう。
今月は最近読んだ雑誌で特集していました『絶対目標達成する人、絶対できない人の思考習慣10~努力には“いい努力”と“そうでない努力”がある。目標を達成できる人は、いかにして“いい努力”を選び取っているのだろうか?』について少しご紹介したいと思います。
(私もですが、、、)誰でも、仕事や普段の生活で目標を達成する為に日々努力をしていると思います。特に日本では「頑張る事、努力する事が大切だ!」という価値観を子供の頃から教えられると感じています。しかし努力というのは“目標を達成する為の手段”だと思えるのは決して私だけではないはずです。
今回の特集では、多くの人が“努力する事自体が目的化してしまっている事”に注目して『目標に最短距離で到達する為の努力とはどんなものか』を10項目記載してありました。私が特に考えさせられた2つを以下に記します。
●『努力しない努力』 or 『いかに努力するか』
ビジネスにおいては、なるべく少ない時間、労力、費用で、できる限り大きな成果を上げる事が求められます。その為には、仕事にとりかかる前に「最小限の努力でゴールにたどり着く為にはどうすれば良いか」を考え、段取りを組む必要があります。つまり「努力しない努力」が重要なのです。以前、私が部下に資料作成を依頼した時の事。その部下はゼロから考えて資料をつくり、かなりの時間をかけて完成させました。しかし多くの資料は、似たようなケースで作成したものが社内に存在します。そうした雛形を活用すれば、最小限の労力で必要な水準の資料を、もっと早く完成させる事ができたかもしれません。仕事をスムーズに進め、高い成果を上げる為には「この努力は本当に必要なのか」を、常に問い続ける必要があるのです。
●『人のマネをするか』 or 『自分らしさを追求するか』
技術や知識を新たに身につけようと思ったら、まずはお手本を見つけてマネする事が成長への近道です。「守破離(しゅはり)」という言葉を聞いた事があるでしょう。千利休が茶道を通して体得したと言われている、人がある道を究めるステップです。「守」とは、習った事を徹底的にマネする段階、「破」とは、守において習得した型に、自分ならこうするという思いを加えてアレンジする段階、そして「離」は、オリジナルを確立していく段階の事です。目標達成できない人は「誰かのマネをしてはいけない」と考えてしまう傾向があります。いきなりオリジナリティを出そうと努力するあまり、壁にぶつかって前に進めなくなってしまいます。オリジナリティは手段でしかありません。仕事において真に問われているのは、手段ではなく目的の達成です。自分らしさはいったん横において、お手本を徹底的にマネする事に取り組んでみてはいかがでしょうか。
皆さんは今回の2項目を読んでみて、どのように考えましたか。私は「努力しない努力」「人のマネをする」の両方とも、古き良き職人さんの世界だなと感じました。職人さんから“段取り八分”という言葉を聞いた事が私はありますし、皆さんの中でも知っている人も多いと思います。必要な物や事を用意したり、事前に打ち合わせしたりする“段取り(準備)”が重要で、その“段取り(準備)”がしっかりできれば80%は完成しているという意味です。又、昔は職人さんの世界では「技術や知識は見て盗め(マネをしろ)」とも言われていました。
時代が変化しても、昔の職人さん達が行なっていた事は今でも重要な事だと考えます。そして「努力しない努力 = 段取り八分」「人のマネをする = 見て盗め」は自分自身でしっかり考えないとできない事だと思います。まずは自分でしっかり考えて“努力しない努力”“人のマネをする”を心掛けて1つでも多くの目標を達成したいと考えています。そして、その後で“自分らしさ”を追求してオリジナリティを確立したいと強く思いました。
(言葉の知らない私は「守破離」を初めて知りました。恥ずかしながら、、、日々勉強ですね、、、)
最後になりますが、今月も「新型コロナウイルス」の経過について記載致します。秋田県内の感染者確認は、引き続き少ないレベルを保っています。全国的にも状況は同じですが、未だに感染者の確認がある事は事実です。又、5月8日には、感染症の分類が“2類相当”から“5類”へ引き下げられ、秋田県内では全64病院での入院受け入れ体制を目指すとの事です。様々な課題や問題があるとは思いますが、真の意味での“Withコロナ”がスタートします。自己判断や自己責任が重要になってきますね。
そして毎回記載していますが、感染者を日々支えて救い続けて頂いている医療従事者並びに関係者の皆様、治療薬やワクチンの開発に尽力して頂いている研究者の皆様、本当に敬服致します。くれぐれもご自愛下さい。
長いようで短い1ヵ月。又1ヵ月後に更新致しますので、お付き合いを宜しくお願い致します。
令和5年5月
社長だより vol.97
新年度、令和5年度がスタートします。皆様、新年度も何卒宜しくお願い致します。そして4月は入社や入学など新たなスタートの時期になります。新たなスタートを迎えた皆さん、環境に慣れなかったり、分からない事があると思いますが、是非とも“楽しんで”日々の活動や生活を送って下さい。
今まで“社長だより”で“語彙力”について4回ほど掲載しました。自身の語彙力の無さを痛感しながら日々研鑽を積んでいるつもりですが、とても難しい事です。意識して生活を送っているからなのか、様々な雑誌やメディア等で“語彙力”についての特集や記事を目にする機会が多々あります。今回も最近読んだ雑誌の中にあった「“できる!”と思われる“大人の語彙力”」について以下に少しだけご紹介致します。
【以下、記事の抜粋になります】
自分の気持ちを正しく伝え、相手の心を動かすために、語彙力は大切です。ポイントは、意識的なインプットとアウトプットです。自然に増える事は無く、トレーニングが重要です。文章を書く時は、言葉の重複を避けると、より深まった表現が出来ます。あなたのメールの文末は「思います」だらけになっていませんか。「思う」は「考える」「感じる」「予想する」など様々な表現に言い換えが出来ます。又、意外と間違った言葉の使い方をしているかもしれません。恥をかく前にチェックする事も大切です。自分の語彙力レベルを点検して、ブラッシュアップして下さい。
①正しいのはどちらでしょう?
「同僚に愛想を振りまく」 ← ×
「同僚に愛嬌を振りまく」 ← ○
【解説】
振りまくのは「愛想」ではなく「愛嬌」が本来の言い方。誰に対してもニコニコと笑顔で接する事をいう。
②正しいのはどちらでしょう?
「シミュレーションは大切だ」 ← ○
「シュミレーションは大切だ」 ← ×
【解説】
「シュミレーション」は誤用。英単語(simulation)の綴りを思い浮かべるとよい。
③正しいのはどちらでしょう?
「力不足かもしれませんが頑張ります」 ← ○
「役不足かもしれませんが頑張ります」 ← ×
【解説】
力量に対して役目が軽すぎるのが「役不足」。役目の方が重すぎると謙遜して言うのは「力不足」を使う。
今回3つの例文を記載しましたが、皆さんは正しい表現(使い方)が分かりましたか。私自身は微妙です(笑) 特に②は誤用していたような気がします。日本人なので日本語を活用すればと思い調べたところ日本語では「模擬」「模擬実験」「模擬訓練」との事です。なんだか変に難しくなってしまいます。やはり今回のインプットを機会に正しく「シミュレーション」を活用していこうと思います。
語彙力と直接関係が無いかもしれませんが言葉繋がりという事で、最近“心が震えた”素敵な言葉を以下に記したいと思います。
「僕から1個だけ。憧れるのを、やめましょう。 (中略) 憧れてしまったら越えられないので。今日僕たちは超える為に、トップになる為に来たので。今日1日だけは彼らへの憧れを捨てて、勝つことだけ考えていきましょう。さあいこう!」
皆さんもご存じの通り、大谷翔平選手がWBC決勝戦で世界最高峰のメジャーリーガー達を目の前にして、試合前の円陣で語った言葉です。語彙力も大切かもしれませんが、、、
やっぱり“気持ち”や“熱意”も人の心を動かす為には重要ですよね!!!
最後になりますが、今年も「新型コロナウイルス」の経過について記載致します。秋田県内の感染者確認は引き続き減少傾向となっています。病床使用率も10%前後を推移しています。全国的にも減少傾向となっていますが、未だに感染者確認がある事は事実です。マスクの着用は個人の判断に委ねられる事になりましたが、感染症の分類は“2類相当”のままで感染した場合や濃厚接触者となった場合の行動制限は変わりません。少しずつコロナ禍以前の生活スタイルに戻っていきますが、まだ基本的な感染防止対策を行なう事が必要だと感じています。
そして毎回記載していますが、感染者を日々支えて救い続けて頂いている医療従事者並びに関係者の皆様、治療薬やワクチンの開発に尽力して頂いている研究者の皆様、本当に敬服致します。くれぐれもご自愛下さい。
長いようで短い1ヵ月。又1ヵ月後に更新致しますので、お付き合いを宜しくお願い致します。
令和5年4月
社長だより vol.96
あっという間に3月です。今年の冬は過ぎてみれば(まだ冬は終わってないかもしれません、、、)積雪が少ない冬でした。筋トレという名の除雪を行なう事も少ないシーズンでした。そして既に道路の積雪もほとんど無く、日々春に近づいていると感じています。もしかしたら“なごり雪”があるかもしれません。気を抜くことなく、安全運転には注意して日々お過ごし下さい。
今回はニューヨークタイムズ紙「2023年に行くべき52ヶ所」で世界2番目に“岩手県盛岡市”が選ばれた事について、ご紹介したいと思います。
今年の1月12日、ニューヨークタイムズ紙の電子版に「2023年に行くべき52ヶ所」が掲載されました。日本から選出されたのは、盛岡市と福岡市(19番目)の2ヶ所でした。因みにこれまでに国内で選ばれたのは、東京、大阪、京都など世界的にも有名な大都市ばかりだったそうです。盛岡市【R5,1,1時点:285,407人(公式HP調べ)】は、人口規模で見ると秋田市【R5,2,1時点:301,984人(公式HP調べ)】より少ない都市です。私も江戸時代には南部藩の城があった歴史ある城下町だった事、“わんこそば”や“冷麺”や“じゃじゃ麺”が有名など、業務上で訪問する機会が多いので多少の知識はあります。そんな盛岡市を「東京から新幹線ですぐ、混雑とは無縁の歩きやすい街」と、ニューヨークタイムズ紙に作家で写真家のクレイグ・モドさんが推薦文を寄せた事が今回の掲載に繋がったとの事です。中山道を歩き街道沿いの喫茶店文化について、記述した著書もあるクレイグ・モドさんが2021年に全国の地方都市を歩き、その価値を見出したのが盛岡市だったそうです。クレイグ・モドさんは「岩手県盛岡市は、しばしば見過ごされ、無視されがちである。(中略)市街地は、非常に歩きやすい。大正時代に建てられた西洋と東洋の建築美が融合した建物、近代的なホテル、いくつかの古い旅館、曲がりくねった川が街中にあふれている。古代の城跡が公園になっているのも魅力のひとつだ」と盛岡市の魅力を記載していました。
このニュースをご存じの方も多いと思いますが、皆さんはどのように感じて何を考えましたか?私は最初にこのニュースを目にした時は、大変恐縮ですが「えっ!なんで盛岡市?」と思いました。(盛岡市の皆様、大変申し訳ございません。) 更には「秋田市だって江戸時代には佐竹藩の久保田城があった歴史ある城下町だったし、今では千秋公園として整備もされている。日本酒やきりたんぽ鍋や稲庭うどんなど飲食でも全国的に美味しいと有名だし、、、確かに東京からは新幹線で少しだけ遠いけど、、、(4時間前後は遠いかもしれませんね。)」と少しだけ悔しさを感じました。と同時によく考えると盛岡市内をしっかり歩いて観て回った事がない事にも気付きました。いつも繁華街(大通りや映画館通り)しか歩く事がないので、今度は是非ゆっくり盛岡市内を歩いて観てクレイグ・モドさんが伝えた魅力をしっかりと感じてみたいと思います。
関連した事項になりますが、宝島社が年1回創刊している「田舎暮らしの本」で「2023年版第11回“住みたい田舎”ベストランキング」において、全国ランキング“人口20万人以上のまち”で秋田市が「総合1位(若者・単身者が住みたいまち1位、シニア世代が住みたいまち1位、子育て世代が住みたいまち4位)」に選出されました。これは移住定住の推進に積極的な自治体を対象に、移住支援策、医療、子育て、自然環境、就労支援、移住者数などについて、自治体からの回答をもとに田舎暮らしの魅力を数値化し、ランキング形式で紹介しているものだそうです。「空路1時間で上京出来てアクセスが良く、テレワーク施設や国際教養大、秋田公立美術大など教育環境が充実している。又、医療福祉施設がバランス良く立地し、65歳以上の市民は一律100円でバスに乗車出来るなど、シニア世代も安心して暮らせる環境がある。」と理由が記載されていました。
“空路1時間で上京出来てアクセスが良く(秋田市)”“東京から新幹線ですぐ(盛岡市)”どちらも個人的感覚にはなりますが「遠いようで近い」「近いようで遠い」ですね。盛岡市と秋田市は往来するのに「遠いようで近い」「近いようで遠い」約2時間かかりますが、お互いに魅力がある事は間違いないと思います。
最後になりますが、今年も「新型コロナウイルス」の経過について記載致します。秋田県内の感染者確認は減少傾向に転じており、独自の警戒レベルも「レベル1」に引き下げられました。病床使用率も20%前後を推移しています。全国的にも減少傾向となっていますが、未だに感染者確認がある事は事実です。そのような状況の中ではありますが、3月13日以降はマスクの着用は個人の判断に委ねられる事になりました。“個人の判断に委ねる事”について賛否両論ですが、少しずつコロナ禍以前の生活スタイルに戻っていきます。しかし今はまだ基本的な感染防止対策を確実に行なう事が必要です。更に感染した場合や可能性がある場合は適切な行動や対応を行なう事も重要です。
そして毎回記載していますが、約3年以上に渡り「新型コロナウイルス」と戦い続け、感染者を日々支えて救い続けて頂いている医療従事者並びに関係者の皆様、治療薬やワクチンの開発に尽力して頂いている研究者の皆様、本当に敬服致します。くれぐれもご自愛下さい。
長いようで短い1ヵ月。又1ヵ月後に更新致しますので、お付き合いを宜しくお願い致します。
令和5年3月
社長だより vol.95
今年の冬は降雪はありますが積雪が少ないですね。しかし寒いと思う日が多いと感じています。そして運転中にも凍結路面で滑ってしまい「あっ!」と息を飲む瞬間が多々あります。皆さんも車間距離を十分に保ち安全運転には注意して日々お過ごし下さい。
今回はビジネス誌で取り上げられていた書籍について、ご紹介したいと思います。“稼ぎにくくて減りやすい「お金の正体」とは”との題名で井原西鶴(さいかく)著「日本永代蔵(にほんえいだいぐら)~現代語訳付き」という江戸前期に出版された書籍の紹介です。お金の成功談と失敗談の両方を様々なエピソードで描き出している日本初のビジネス小説と呼ぶべき作品との事でした。「お金を儲けたい」「お金で失敗したくない」などという普遍的な欲求は(勿論私もですが、、、)人間誰しもが多かれ少なかれ抱いていると思います。江戸時代の人々もその思いは同じだったらしく、本書籍は今で言う“ベストセラー”となったそうです。紹介されていたエピソードを以下に記します。
【成功談~味噌の販売で大成功した商人】
それまで味噌は、どの店でも子桶や俵に入れて売られていました。しかし重くて運ぶのが大変だし、子桶や俵を作るのに多額の費用がかかります。そこでこの商人は、味噌を少量ずつ蓮の葉に包んで売ろうと思いつきます。しかもその蓮の葉は、世間の人達がお盆のお供え物を川に流した時に拾い集めてくるので、ただで手に入ります。コストがかからないうえ、お客にとっては手頃で買いやすいので、たちまち大繁盛しました。
商人が小売りのアイデアを思い付いた事を、著者の井原西鶴は次のように表現しています。
『この親仁(おやじ)、工夫仕出して』
現代語に訳すと「この親仁(おやじ)が新しく工夫して」という意味になります。つまりは成功の理由は「工夫」にあったわけです。お金を儲けるには才覚が必要ですが、それはつまり「より良い方法を工夫出来る事」を意味するのです。
【失敗談~味噌の販売で大成功した商人一家、その後】
商人自身はビジネスの成功に浮かれる事なく堅実な生活を続けたものの、その息子が鉱山に投資して失敗し、親父が40年かけて稼ぎ出したお金を、わずか6年で使い果たしてしまったのです。残念ながら、息子には工夫出来るだけの才覚がなかったのでしょう。
『金銀はまふけがたくて減りやすい』
お金というのは、儲けにくくて減りやすいものだ。井原西鶴もこう綴っているように、お金とは本来、そう簡単には儲からないという事です。
エピソードを読んで皆さんは何を思い、何を考えましたか。私は“考える事”の大切さと“堅実さ”の重要性を再認識しました。そして当たり前の事ですが“お金は簡単には儲からない”との思いを強く持つと共に“投資の怖さ”を痛感しました。更にはアイデアとは、特別なところではなく普段の日常生活の中に潜んでいる事、ただ淡々と業務をこなすのではなく(工夫が可能か)考えながら取り組む事が重要だとも感じました。私の業務や生活の中にも潜在的なニーズや工夫可能なアイデアが潜んでいるはずです。お金を儲けるまでいかなくとも、せめて生活を豊かに楽しくする為にも、ボーッとせずに色々考えながら行動していきます。(皆さんも如何ですか?)
因みに書籍紹介の記事を読んで直ぐにスマホでポチっと購入しました。江戸時代前期という約400年前のベストセラーをネットで購入、、、何だか不思議な感覚です。
最後になりますが、今年も「新型コロナウイルス」の経過について記載致します。秋田県内の感染者確認は減少傾向に転じ14日連続で前週同曜日を下回り、病床使用率も20%台まで減少しました。全国的にも減少傾向となっていますが、未だ秋田県内でも連日3桁の感染者確認がある事は事実です。そのような状況の中でコロナ禍以前の生活スタイルには戻る事はないまでも、経済活動との両立“Withコロナ”の生活を行なっています。又、政府は今年5月8日には新型コロナウイルス感染症の分類を現在の“2類相当”から“5類”に引き下げる方針を掲げました。色々と準備や乗り越えなくてはいけない壁も多々ありますが、もう少しで真の“Withコロナ生活”となります。
しかし今はまだ基本的な感染防止対策を確実に行なう事が必要です。更に感染した場合や可能性がある場合は適切な行動や対応を行なう事も重要です。
そして毎回記載していますが、約3年もの期間に渡り「新型コロナウイルス」と戦い続け、感染者を日々支えて救い続けて頂いている医療従事者並びに関係者の皆様、治療薬やワクチンの開発に尽力して頂いている研究者の皆様、本当に敬服致します。くれぐれもご自愛下さい。
長いようで短い1ヵ月。又1ヵ月後に更新致しますので、お付き合いを宜しくお願い致します。
令和5年2月
社長だより vol.94
謹んで新春のお慶びを申し上げます。本年も良い年になりますように心からお祈り致します。
令和5年(2023年)も何卒宜しくお願い致します。今年は「卯(うさぎ)年」になります。漢字の「卯」は、門を無理に押しあけて中に入りこむ様子を表した字で、草木が伸び出て地面を覆うようになった状態を表すとも解釈されています。中国伝来の十二支は、もともと植物が循環する様子を表しているので、十二支の4番目に茎や葉が大きくなる様子を表す「卯」がくるとの事です。(子年に新しい命が種の中で芽生えはじめ、丑年には種の中で育つがまだ伸びる事ができず、寅年は春が来て根や茎が生じて成長する時期と言われています。)
そして卯(うさぎ)は穏やかで温厚な性質であることから、「家内安全」。又、その跳躍する姿から「飛躍」、「向上」を象徴するものとして親しまれてきました。先にも記載しましたが「植物の成長」という意味もあり、新しいことに挑戦するのに最適な年と言われています。
関連した事柄になりますが、株式相場には【辰巳天井、午尻下がり、未辛抱、申酉騒ぐ、戌は笑い、亥固まる、子は繁栄、丑はつまずき、寅千里を走り、卯は跳ねる。】という格言があるそうです。兎には跳ねる特徴があるため、景気が上向きに跳ねる、回復すると言われており、株式市場にとっては縁起の良い年として知られているようです。←←←是非ともそのようになって欲しいものです。
又、本来の干支とは「十二支(じゅうにし)」」と「十干(じっかん)」を組み合わせるものだそうです。十二支とは時間を表し、「子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥」の12種の動物を当てはめています。この十二支に、空間を表す十干「甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸」の10の要素を加えたのが、60種からなる「干支」です。双方を組み合わせた干支を六十干支(ろくじっかんし)ともいい、60年で一巡します。
2023年の卯年は「癸卯(みずのとう)」だそうです。「癸(みずのと)」は順序で言えば最後にあたり、一つの物事が収まり次の物事への移行をしていく段階。又、「卯(う)」のうさぎは「茂」という時期であり、繁殖する、増えるという段階にあたると言われています。その両方を備えた「癸卯」は、去年までで様々なことの区切りがつき、次へと向かっていく、そこに成長や増殖といった明るい世界が広がっていくと解釈することが出来ます。
色々調べてみると2023年、良い年になりそうですね。私も新しい事にチャレンジして“卯(うさぎ)”のように跳ね(飛躍)上がり(向上)、自分自身の力で良い年にしようと思います。
又、“癸卯(みずのとう)”の意味のごとく、約3年間も生活に影響を与え続ける“新型コロナウイルス感染”に区切りがついて、次の新しい明るい状態へ移行する事を切に願っています。
最後になりますが、今年最初も「新型コロナウイルス」の経過について記載致します。感染者の確認は高止まり状態となっており、秋田県内でも連日三桁の感染者の確認があります。更には季節性インフルエンザとの同時流行に警戒感が示され、既に東京や東北の青森県や岩手県では感染率が高まっている状況です。しかし私達は、コロナ禍以前の生活スタイルには戻る事はないまでも、経済活動との両立“Withコロナ”の生活を行なっています。だからこそ基本的な感染防止対策を確実に行なう事が未だ必要です。更に感染した場合や可能性がある場合は適切な行動や対応を行なう事も重要です。
そして毎回記載していますが、年末年始の休暇も返上して「新型コロナウイルス」と戦い続け、感染者を日々支えて救い続けて頂いている医療従事者並びに関係者の皆様、治療薬やワクチンの開発に尽力して頂いている研究者の皆様、本当に敬服致します。くれぐれもご自愛下さい。
長いようで短い1ヵ月。又1ヵ月後に更新致しますので、お付き合いを宜しくお願い致します。
令和5年1月
社長だより vol.93
早いもので2022年も残り1ヵ月となりました。今年も2020年から続く“コロナ禍”で、様々な制限や我慢、困難や努力を強いられた1年となりました。現在も新型コロナウイルス感染は終息していませんが、コロナとの共生“Withコロナ”での新たな活動が行われています。一昨年と昨年の12月にも記載しましたが“明けない夜はない”“朝の来ない夜はない”との思いを胸に日々を過ごしていきたいと思います。そして1日も早く、以前のような平穏な日々を過ごせる事を心より祈念致します。
先日ある講演会で心理学を専攻している准教授の話をお聞きしました。「コロナやストレスに負けない!」との演題で90分間の講演でしたが、引き込まれてあっという間に終わりました。健康で過ごす為には「ポジティブシンキングで幸福感を得る事」が重要であるとの内容で非常に考えさせられました。今回は講演内容と更には最近読んだ雑誌に掲載されていた関連記事?を紹介したいと思います。
(講演内容については、私のメモと記憶で記載していますので、多少違いがあるかもしれませんがお許し下さい。)
講演では「幸福感を得る事が健康に繋がる」を実践する為には“人に感謝する”“人を援助する”“人に安心感を与える”事が重要だと話をされていました。更に“安心感を与える”方法として「どのような状況でも“大丈夫だよ”の気持ち」「相手を受け入れる」「自分と相手の居場所を確保する」「見守り、理解する」事が必要だとも話をされていました。又、関連してポジティブシンキングの手法の1つとして「リフレーミング」をご紹介頂きました。リフレーミングとは「物事を見る枠組み(フレーム)を変えて、違う視点で捉え、ポジティブに解釈する事」で、簡単に言えば「言い方や表現を変換する手法」です。一例を挙げれば「あなたは短気ですね」というネガティブな表現を「あなたは自分の感情に素直ですね」とポジティブに変換する事です。ポジティブな表現や言葉を発する事で自然と幸せな気持ちになるとの事でした。
自身が幸福感を得て健康になる為には、人(他人)に対しての行動が重要である事に多少驚きましたが、人間は一人では生きていけないとの思いを再確認させて頂きました。又、私自身が以前から気を付けている“ポジティブシンキング”についても、考えるだけでなく“リフレーミング”を用いて、発する言葉(表現)にも注意していこうと改めて思いました。
(関連した?雑誌の記事について…)
先日ある雑誌を読んでいると「沖縄県民が幸せな理由」とのコラムに目が留まりました。都道府県“幸福度”ランキングで沖縄県が2年連続1位となった理由が「適当である県民性」だとの記載でした。私は「えっ?ディスってる?」と感じて詳細を読んでみました。すると『沖縄県民には「ウチナータイム」が存在すると言われていて、時間の感覚が非常にゆったりとしています。時間厳守が当たり前の人にとっては「いい加減」ともいえる県民性が、実は沖縄県を日本一幸せにしている要因です。』『時間にルーズな人の方が、几帳面な人より幸福という事が研究で分かっています。』『世界的に見ても「時間を守る」という事の優先順位が低い国は少なくありません。』『最終的には、幸福になりたければ時間を厳守せずにルーズになりなさいと言うつもりはありません。幸せになる為に必要なものは、ずばり“寛容さ”です。』との記載がありました。そして結びに『沖縄県民がよく口にする「ナンクルナイサー」という言葉は、正しくは「マクトゥソーケーナンクルナイサー」。誠実にやるべき事をきちんとしていれば、何とかなるよ、という意味です。つまり「どれだけ適当でも、時間に遅れても、何とかなるよ」ではなく、やるべき事をやっている事が大前提なのです』と記載がありました。
私は比較的、時間にはうるさい方です。(たまに飲み過ぎて寝坊する事もありますが、、、)時間厳守は小さい頃から叩き込まれてきた一種の礼儀だと思っています。しかし今回この記事では、沖縄県を例にとって「寛容さ = 広い心をもち、他を受け入れる気持ち」「他者に寛容な社会」が幸せに繋がる事を教えて頂きました。
今回ご紹介した2つには共通点が沢山あります。健康で過ごす為に、幸せに過ごす為に皆さんも是非“ポジティブ”に、そして“やるべき事をしっかりやる事”を前提にして“他者を受け入れる寛容な心を持って”頂ければ幸いです。
最後になりますが、今月も「新型コロナウイルス」の経過について記載致します。感染者の確認は増加傾向に転じており、第8波に突入?との報道もあります。秋田県内でも連日四桁の感染確認があります。更には季節性インフルエンザとの同時流行の可能性が高い事も予想されています。そのような状況の中ですが、コロナ禍以前の生活スタイルには戻る事はないまでも、経済活動との両立“Withコロナ”の生活を行なっています。だからこそ私達は基本的な感染防止対策を確実に行なう事が未だ必要です。そして感染した場合や可能性がある場合は適切な行動や対応を行なう事も重要です。
更に毎回記載していますが、拡大と減少を繰り返し続けている「新型コロナウイルス」と戦い続け、感染者を昼夜問わず日々支えて救い続けて頂いている医療従事者並びに関係者の皆様、治療薬やワクチンの開発に尽力して頂いている研究者の皆様、本当に敬服致します。くれぐれもご自愛下さい。
長いようで短い1ヵ月。又1ヵ月後に更新致しますので、お付き合いを宜しくお願い致します。
令和4年12月