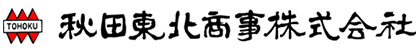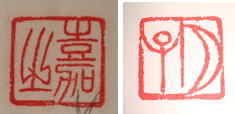社長だより vol.20
【文房四宝 その3】
東京在住の方から『おつえと信助の「TO BE CONTINUE」』、続けて、『筆職人信助の作る立派な筆、しかしながら文房四宝のうち使っていくと価値が落ちていくのは筆。鑑賞するには筆毛の管理が大変。墨や硯と筆の違うあやうさ、はかなさを藤沢周平は男と女の間に象徴的に潜り込ませたのでしょうか。はたまた墨に染まった筆毛はもう元には戻れないのか・・』とメールを頂戴しました。
実は、小説の終盤に「信助の届けた筆をおつえが手入れを怠ったため虫食いでボロボロになり、筆を折ろうとしたこと、信助との間が終わったとして泣きつくしたこと、この筆に“輝くようだった若い時分の残光をみて”過去の思い出として大切に保管しようとした」ことが書かれています。そして、結びは、間もなく人手に渡る『暗く長い廊下を歩きながら、おつえは夫に優しい言葉をかけてやりたい気持ちになっている』で終わっているのです。この時の情景を中一弥の挿絵がすべてを呑み込んだかのようにしっとりとラストを飾っています。
実際の挿絵は“てぷっとした”夫が行燈の前に紋付羽織を着て力なく後ろ向きで酒を飲んでいる。おつえは立ち上がって背中合わせだが、声をかけようかと切れ長の目で夫の背中を見ている・・・そんな情景を想像してください。引用は昭和54年5月号太陽特集小説 藤沢周平 歳月より。
ムクゲは八重の赤紫、一重の赤紫と白の3種がある。クチナシは冬囲いをしてやるのだが毎年春に殆ど葉を落とし、心配させるが新芽を吹きだし、甘い香りの真っ白な花を咲かせてくれる。のうぜんかずらは父の大好きな花の一つ、前の家にあったものを銀杏ごと移植したもの。高さは5mもあろうか、土崎の曳山あたりに咲き始め、本格的な夏到来を教える。
私の文房具の中で心残りの硯がある。厚みが5センチぐらいで何の飾りもない手のひらにすっぽり入るような楕円の端渓だ。艶やかながら深みのある漆黒。目の前から見えなくなって20年にもなる。どこに去(い)ってしまったのだろう。墨色の中を流れてゆく私の思いは届くのだろうか。墨色というと福島弘樹さんの文鎮(氏のオブジェとしての芸術作品だが、勝手に私が文鎮と言っている)がある。鉄と銅の合金だ。印材と一緒に眺めていると金属ながら優しく話しかけてくるような温もりを感ずる。
印影も実に面白く和やかさを与えてくれる。写真は私と母(夕子)の朱文の印影。どちらも40年近く前、専門家に篆刻してもらったものだが気に入っている。白文もあるが、「嘉」の字が「由」で届けられ、お蔵入りしている。秋田の長い冬の楽しみは篆刻にして印譜でも作ろうか。書もいいが、印影の自由奔放さは人に見せることもなく気楽で楽しい。書や日本画の展覧会に出掛けても白黒と余白に朱の印影はことさら気になる。

文箱の蓋を開けて、いざ写経、準備はできているがその気になって心を摩っている。これを幾度となく繰り返しているのだからいやはや何とも滑稽な話だ。印肉は丸い磁器製の印池に入っている。ふたの裏に光明朱砂印泥、一両(四文匁:よんもんめ)とある。水滴・筆洗・筆架・印材・筆筒・鎮紙(文鎮)など眺めて愛らしい文房具は、私のような凡人には憧れへの思索に欠かせない道具たちだ。(文房四宝おわり)
平成28年8月