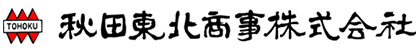エコムジャーナル 特別号Vol.4
【駅】
2022年3月1日の日本経済新聞、コラム「春秋」に『「駅」という言葉は、どこかもの悲しい。これまで、どれほどの人びとの出会いや離別の場になったのか。古里の駅から戦地に出征する親族を見送った。でも、それが今生の別れになってしまった。セピア色のつらい記憶を持つ戦中世代の方も、おられるかもしれない。』とある。私から平和の3駅をご紹介する。
駅といえば、ベニスを舞台としたキャサリン・ヘプバーンの「旅情」、あの最後のシーン。アメリカに帰る婚期を逃した彼女を乗せた汽車が動き出す。ホームにやや小柄な中年の恋の相手が白い花を掲げて走ってくる。窓から大きく身を乗り出し懸命に手をふる、あのシーンだ。さすがお国柄、イタリアだ。ゴンドラのシーンでは「オーソレミヨ」、いたるところで「カタリ」・「パッショーネ」などカンツオーネの名曲がながれた。
小生の浪人生活は仙台であり、仙台駅で苦い思いの洗礼を受けた駅だ。当時の駅舎の正門は大きなぎーぎー鳴る木製のガタガタ扉。実家から連絡のあった時間にこの扉の前で叔父を待った。ほどなくニコニコ顔で近づいてきて、元気か?ぐらいの話はしたと思うが詳細な記憶はもちろんない。しかし、母から下宿の電話に叔父の話として、“着ていたものはさもしいものとの印象”で、力を落とした声が今も耳に遺る。
今年91歳になる従兄の新婚旅行。結婚式を当時の国鉄宿泊所で挙げ、その足で従兄たちが秋田駅に集まった。勿論見送りだ。記憶ははっきりしないが、“夜行急行つがる”だったと思う。今ではNHKアーカイブに登場するようなホームで“頑張れ、頑張れ”などと大声を張り上げた記憶がある。何を頑張れと言ったのかわからないが、後にも先にもホームでの新婚旅行の見送りはこれ1回しかない。
春秋の最後は『ウクライナ国境に近いポーランド南東部の街、プシェミシルの駅舎の光景を現地入りした記者が伝えた。戦乱を逃れた女性の肉声が胸に迫る。一方、この駅に向かうウクライナの男たちの姿も、メディアは報じる。近隣国での出稼ぎを中止し、祖国防衛に赴くのだ。映画ではない。この世界の現実である。』、と伝える。あのひまわり畑は大丈夫なのだろうか。